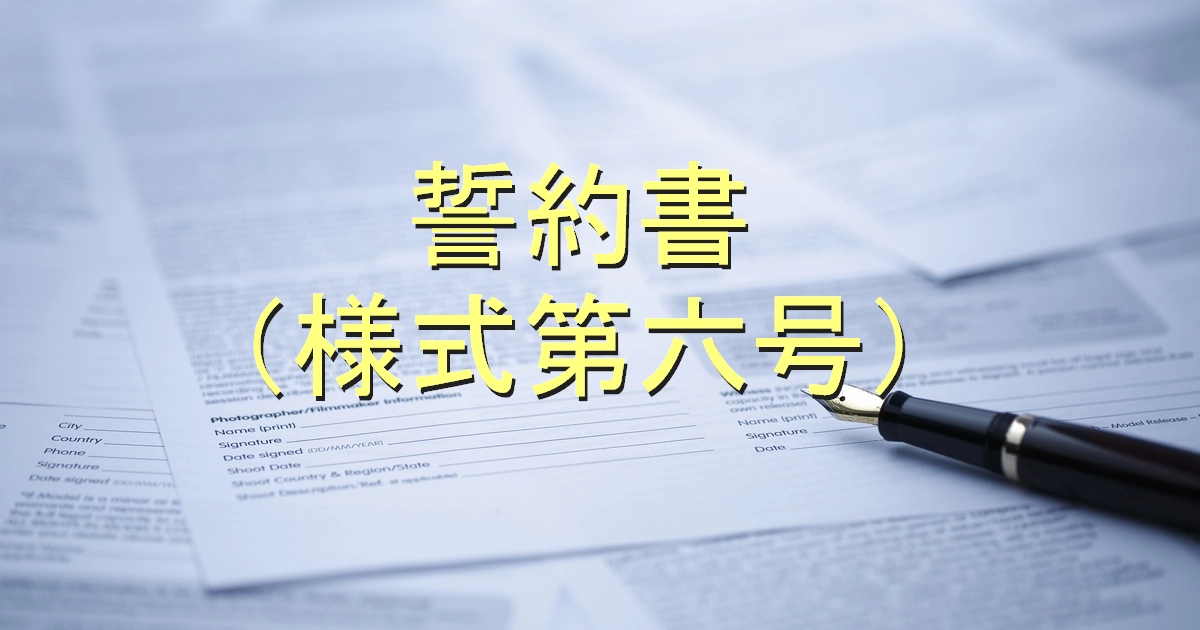建設業許可の申請では、誓約書(別記様式第六号)を正しく整えることが合否を左右します。本稿では、誓約書の法的位置づけや対象者の範囲、申請先の判定、紙と電子それぞれの書き方、よくあるミスと対処、更新や変更届、さらにはCCUSまで、現場で迷いがちなポイントを順番に整理します。専門用語はできるだけ噛み砕いて説明しますので、初めての方でも安心して読み進めてください。
誓約書(別記様式第六号)とは?
法的な位置づけ
誓約書は建設業法6条1項4号に基づく必須添付書類で、建設業法施行規則の別記様式第六号として全国統一で定められています。各自治体が配布するPDFは体裁の違いがあるものの、内容はこの統一様式に準拠します。様式の文言は定型であり、独自に加筆修正せず、そのまま用いるのが原則です。
誓約の対象者
誓約の対象は申請者本人に限られません。法人であれば役員等と政令3条使用人、個人事業であれば本人に加えて政令3条使用人、そして法定代理人も含まれます。これらの全員が建設業法8条の欠格要件に該当しないことを誓う書面が誓約書です。対象者の捉え方を狭く考えると提出後に補正となり、手戻りの原因になります。
宛名と申請先の正しい判断方法
申請先は営業所の広がりで決まる
申請先は一般許可か特定許可かではなく、営業所の分布で決まります。営業所が一つの都道府県内に収まる場合は都道府県知事、二つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣が申請先です。この基準を正しく押さえることで、宛名の誤りを防げます。
宛名の書き方
宛名は「〇〇県知事 殿」または「国土交通大臣 殿」と明確に記載します。宛名の誤りはそれだけで補正の対象となり、審査の遅延につながります。申請先の判定と宛名の整合を、提出前に必ず確認してください。
記入前の準備ポイント
対象者の確認方法
まず、代表者、役員等、政令3条使用人、法定代理人の名簿を作成し、漏れがないかを確認します。氏名や住所、生年月日などの詳細情報は、誓約書そのものではなく、別記様式の調書(自治体手引の該当様式)で扱うのが一般的です。誓約書に個票情報を過剰に書き込もうとして混乱するケースが多いため、情報の置き場所を最初に整理しておくと後工程が安定します。
添付書類と電子申請の確認
破産の復権証明など、自治体手引で別途求められる添付書類がある場合は早めに取得計画を立てます。併せて、自治体がJCIP(建設業許可・経審電子申請システム)に対応しているか、押印の要否や入力仕様がどうなっているかを最新の案内で確認します。紙と電子では運用が異なるため、最初に方針を決めておくと迷いが減ります。
誓約書の記入手順(紙申請の基本)
宛名と申請者情報
最初に宛名を確定し、申請者情報を様式どおりに記載します。法人は商号を株式会社等の種別まで含めた正式名称で、本店所在地と代表者の職名・氏名を記載します。個人は氏名と住所を住民票記載と一致させます。役員等や政令3条使用人の詳細情報は誓約書ではなく調書で管理する前提で、誓約書側は必要最小限の記載に留めます。
誓約文と日付
誓約文は定型ですので改変せず、そのまま用います。日付は提出日付近を原則とし、未来日付は用いません。書類全体で元号か西暦のどちらかに統一する点も重要です。混在すると軽微であっても補正の対象になり、余計な手戻りが生じます。
署名・押印と訂正の扱い
紙申請で押印が必要かどうかは自治体の指示に従ってください。電子申請(JCIP)では押印省略が基本です。誤記の訂正は修正液や修正テープを使わず、実務では差し替え(再出力)が原則です。訂正印での修正を許容するかは窓口判断に幅があるため、迷う場合は担当課に事前確認するのが最も確実です。
よくあるミスと対処
対象者漏れと情報不一致
政令3条使用人や法定代理人を誓約の対象から漏らす事例が目立ちます。提出直前に対象者名簿と調書を突き合わせ、誓約書と他書類の整合を確認してください。住所の表記揺れや誤字も頻出するため、登記や住民票と完全一致しているか、丁寧に見直します。
宛名誤りと日付の混在
宛名は営業所の広がりに基づく判定結果と一致しているかを確認します。日付は書類一式で元号か西暦のどちらかに統一し、提出日付近に合わせます。工程の初期段階で統一ルールを決めておくと、関係者間の共有がスムーズです。
誓約文の改変
誓約文に任意の追記や言い回しの変更を行うのは避けてください。様式の原文どおりに用いることで、不要な補正や差し戻しを防げます。
不備・虚偽記載のリスク
補正か不許可かの線引き
誤記や軽微な記載漏れは通常、補正での是正が可能です。一方で、重要事項の欠落や虚偽の申告がある場合は、許可の不許可や許可取消、営業停止の対象となり得ます。欠格要件に該当する事実があると判断されれば、裁量的な総合判断ではなく、条文に従って許可不可となります。
罰則のイメージ
虚偽や不正な手段で許可や更新を得た場合は、最重で三年以下の懲役または三百万円以下の罰金が科され得ます。法人には一億円以下の罰金が適用される両罰規定も想定されます。申請書や添付書面に虚偽の記載を行った場合も、六月以下の懲役または百万円以下の罰金が科され得ます。量刑は事案ごとに異なるため、迷う場合は専門家に相談してください。
更新申請での取り扱い
添付省略と誓約書の必要性
更新申請では、工事経歴や施工金額、使用人数に関する書類など六条一項一号から三号の一部が省略できる運用があります。しかし、四号にあたる誓約書は引き続き必要です。新規と同様に対象者の範囲と誓約内容を丁寧に確認し、漏れのないよう準備します。
変更届の期限と運用
期限の考え方
変更届の提出期限は変更内容によって異なります。経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、役員の就退任などは十四日以内、商号の変更や本店移転、営業所の新設や廃止などは三十日以内が目安です。事業年度終了届はいわゆる決算変更届で、事業年度の終了から四か月以内が提出期限です。期限を過ぎると過料等の対象となり得るため、各庁の手引にある期限表を基準にスケジュールを組むことが大切です。
スケジュール管理の勘所
変更は突発的に発生することが多いため、社内で発生通知のルートを決め、法務や総務と情報を即時共有できる体制を整えると遅延を防げます。提出に必要な添付や証明書の取得期間を逆算し、余裕を持った準備を心がけてください。
電子申請(JCIP)のポイント
対応状況と仕様
JCIPの対応は自治体により実装状況が異なります。利用可否、押印の要否、入力項目やアップロード形式など、最新の案内に沿って準備してください。紙申請の感覚でPDFを直接加工しようとすると、フォーマット不一致が生じることがあります。システムの仕様に忠実に入力することが最短経路です。
データ整合の重要性
電子申請では、氏名や住所の表記ゆれが原因でシステム照合に引っかかることがあります。登記や住民票、調書、誓約書の記載を同一表記に揃え、変換ミスを避けるために最終段階で一括確認を行うと安心です。
CCUSと周辺実務
義務化されるケース
技能実習の受入れにおいては、CCUSへの登録が義務化されています。該当する場合は、申請スケジュールの初期段階からCCUSの手続きを並行して進めると後戻りが少なくなります。
特定技能への向き合い方
特定技能の分野では、就労管理の運用上、CCUSの活用を求められる場面が存在しますが、法的に一律の義務であると断定することはできません。最新の運用要領と自治体の案内を確認し、案件ごとに適切な対応を選択してください。
事業者にとってのメリット
CCUSは技能や資格、就業履歴を可視化できる仕組みであり、現場の配員や評価、人材育成の計画に役立ちます。公共調達における評価項目として取り扱われる場面もあるため、中長期的な経営の視点から取り入れておくと、実務上の手当てがしやすくなります。
提出前の最終確認
宛名と申請者情報
宛名が申請先の判定結果と一致しているか、申請者の名称や住所が登記や住民票の記載と完全に一致しているかを確認します。ここでの食い違いは補正の最頻出ポイントです。
対象者と調書の整合
誓約の対象者を網羅できているか、調書に記載した個票情報と誓約書側の記載に齟齬がないかを丁寧に見直します。対象者の捉え方を広く取り、迷った場合は調書側の記載を先に確定させてから誓約書を仕上げると効率的です。
様式の厳守と統一
誓約文は様式の定型どおりに用い、日付は提出日付近で、書類全体の表記を元号か西暦のどちらかに統一します。用語や住所表記の統一は、紙でも電子でもミス削減に直結します。
紙と電子それぞれの注意点
紙申請では押印の要否や訂正方法について、電子申請ではJCIPの仕様やアップロード形式について、いずれも自治体の最新案内に従うことが肝心です。不明点は早めに所管課へ問い合わせると、補正のリスクを最小化できます。
まとめ
誓約書は、申請者本人だけでなく、役員等や政令3条使用人、法定代理人を含む関係者全員が欠格要件に該当しないことを示す、重みのある書類です。申請先は営業所の広がりで決まり、宛名はその結果に合わせて正しく記載します。様式どおりの記入、日付や表記の統一、調書との整合が整っていれば、補正や差し戻しは大幅に減らせます。更新や変更届、CCUSといった周辺実務も合わせて管理し、迷いがあればためらわず担当課や専門家に相談してください。正確に、丁寧に、一度で通す。その姿勢が、最短で確実な許可取得につながります。