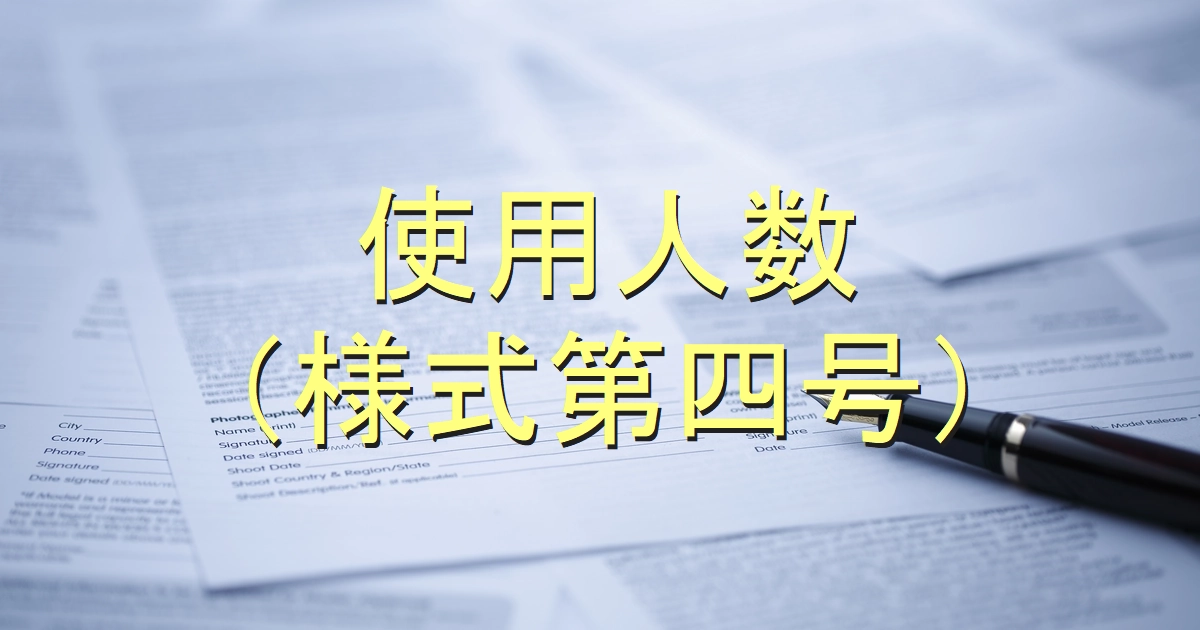建設業許可の「使用人数(様式第四号)」とは、申請者が営業所において常時使用する従業員数を記載するための様式です。これは単なる人数報告ではなく、事業所の人的体制を明示する重要な情報として、許可行政庁が組織の健全性や実態を判断する材料となります。
ただし、様式第四号は新規申請時には原則必要ですが、更新や一部変更届の際には提出が不要な場合もあります。手続きごとの提出要否については、各都道府県の運用を確認することが不可欠です。
使用人数としてカウントすべき従業員とは?
カウント対象となる従業員
- 常勤の役員
- 常勤の技術職員
- 常勤の事務職員
「常時使用」とは、週30〜40時間程度の勤務が継続的に行われている状態を指します。雇用形態(正社員・パート等)よりも、実際の勤務状況が重視されます。
⚠️以下のようなケースは要注意
- 短時間パート(週20時間未満):原則としてカウント対象外。
- 派遣社員:直接雇用でなければカウント不可。
- 無報酬の非常勤役員:原則として使用人数に含めません。
技術職員の記載ルールと資格証明
技術職員としてカウントできるのは、建設業法で定められた資格や実務経験を有する者に限られます。例としては以下のような人材が該当します。
- 1級・2級建築士、施工管理技士などの国家資格者
- 指定学科卒業後、一定年数以上の実務経験者
加えて、これらの者が営業所に常勤していることが必須です。常勤性は、雇用契約書や社会保険加入状況などによって裏付ける必要があります。
事務職員の記載範囲と判断基準
経理、人事、総務など、現場ではなく企業運営に関与する職員が該当します。パートであっても、実質的に常勤であればカウント可能です。ただし、次の点に注意が必要です:
- 勤務実態が短時間で断続的な場合は対象外
- 兼任役員であっても、実態として事務業務に常勤していれば可
報酬の有無ではなく、常勤性が判断基準です。
よくある誤解①:兼業従業員の扱い
複数の業務を兼務する従業員は、主たる職務に基づいて1人分としてカウントします。たとえば、経理と技術職を兼任している場合、勤務時間の過半を占める職務に基づいてどちらか一方に1名分として記載します。
❌ 0.8人+0.2人などの記載は不可です。
提出タイミングと変更時の対応
● 提出が必要な主なケース
| 手続内容 | 様式第四号の提出要否 |
|---|---|
| 新規申請 | 必須 |
| 更新申請 | 原則不要(自治体による) |
| 営業所変更や技術者退職などの変更届 | 通常は不要(他書類で対応) |
退職者の情報変更は、様式第四号を修正して再提出するのではなく、必要に応じて「変更届」や「専任技術者証明書」等を別途提出します。
記入上の注意点と実務でのポイント
● 基本情報(営業所名、所在地、申請日)
- 営業所名や所在地は、登記簿謄本と一致させる。
- 申請日は和暦か西暦で統一する。
● 使用人数の内訳
- 人数は正確に、かつ主たる業務ごとに分けて記載。
- 合計人数との整合性が取れているか要確認。
電子申請の活用について
建設業許可申請は、一部の自治体で電子申請が可能です。利便性は高まりますが、印紙代の免除はありません。電子証明書の取得や書類スキャンの準備が必要なため、事前準備が重要です。
【参考】国土交通省 建設業電子申請システム
https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001
専門家のサポートを活用する意義
書類の整合性、常勤性の証明方法、添付書類の選定など、実務では判断に迷う点が多くあります。行政書士等の専門家に相談すれば、適切なアドバイスとともに申請がスムーズに進み、許可取得の可能性が高まります。
まとめ:使用人数(様式第四号)の正しい理解が成功の第一歩
「使用人数(様式第四号)」は、単なる人数記入欄ではなく、申請者の人的体制を適切に表す重要な書類です。常勤性・主たる職務・兼任の取扱いなどを正しく理解し、申請書全体との整合性を保つことが、許可取得の近道になります。
専門家の支援も活用しながら、正確で漏れのない申請を目指しましょう。