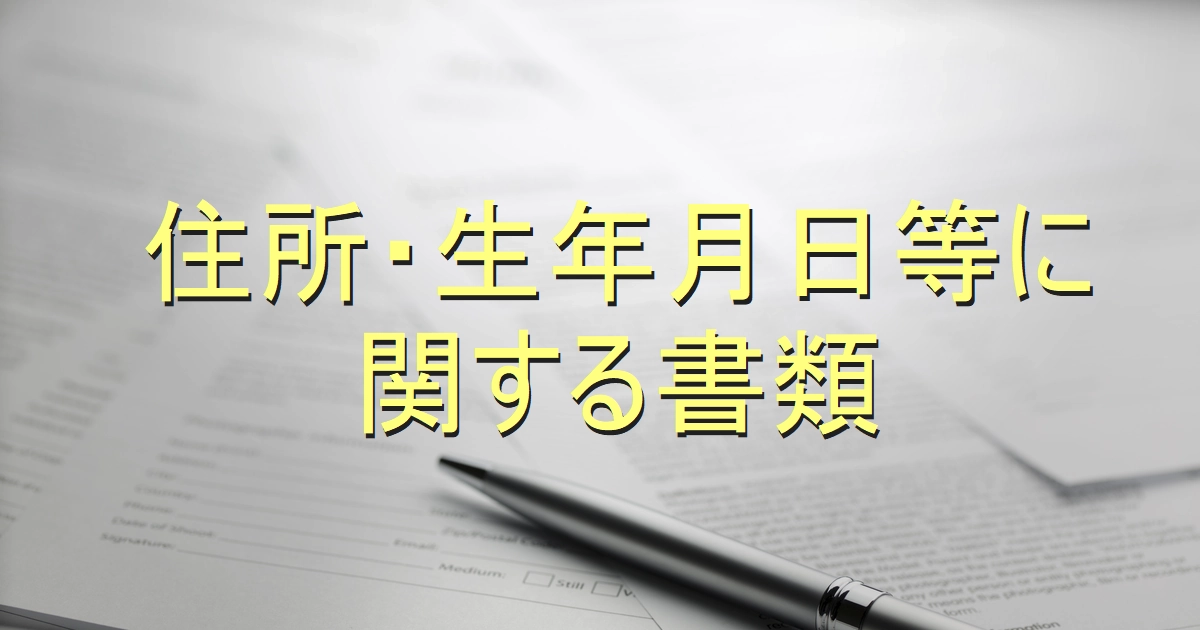建設業許可申請にあたっては、申請者自身や法人役員などの個人情報を記載する「住所・生年月日等に関する書類(以下、本書類)」の提出が必要です。
この書類は、申請者が建設業法に定める欠格要件に該当しないことを確認するための基礎資料となり、申請の可否に直結する重要な役割を果たします。
この記事では、実際の記載例と注意点をもとに、書類作成のポイントをわかりやすく解説します。
本書類の正式名称と提出対象者を理解しよう
都道府県によって名称は異なる点に注意
一般に「住所・生年月日等に関する調書」と呼ばれることもありますが、正式名称は都道府県によって異なり、「役員等の略歴書」「様式第七号」などの表記が用いられます。
誰の情報を記載する書類か
次のいずれかに該当する人物の情報を記載します。
- 法人の場合:代表取締役を含むすべての役員(取締役・監査役等)
- 個人事業主の場合:事業主本人
- ※「令第3条の使用人(支店長等)」については、本書類ではなく「使用人一覧表」や「略歴書」の提出が別途求められます
本書類が必要となる主なケース
本書類は、以下のようなタイミングで提出が求められます。
必要となる主な申請タイミング
ちょっとした見落としで申請が差し戻されることも。本書類が必要になる主な場面を確認しましょう:
- 新規の建設業許可申請
- 業種追加申請(新たな業種を加える場合)
- 許可の更新申請(5年ごと)
- 役員変更があった場合の変更届出
※住所変更のみでこの書類が必要かどうかは都道府県ごとに異なるため、必ず事前に確認を。
👉 まとめ:申請や届出の種類によって必要書類が異なります。手引きや担当窓口での確認を怠らないことがトラブル回避のカギです。
記載例と注意点:書き間違えを防ぐポイント
「うっかりミス」が申請不受理につながることも。本書類の記載項目ごとの注意点を以下にまとめました。
住所の記載
- 住民票に記載された住所を正確に記入します(例:マンション名・部屋番号を省略しない)。
- 転居直後などで住民票と実際の居住地が異なる場合は、基本的には住民票を移した上で申請するのが望ましいです。
- 都道府県によっては、住民票との一致が確認できない場合、申請を受理しない運用となっていることもあります。
生年月日の記載
- 原則として元号(例:昭和55年4月1日)で記載します。西暦の併記は不要または禁止されている場合もあるため、手引きに従ってください。
- 戸籍謄本や住民票と異なる記載をした場合、訂正を求められます。修正歴がある場合は、説明資料の添付が求められることもあります。
氏名・本籍地・役職などの記載
- 氏名は戸籍記載通りに正確に記載します。
- 本籍地は現住所と異なることがあるため、住民票などを参照のうえ正確に。
- 役職は「代表取締役」や「取締役」など、登記簿記載の役職をそのまま記入してください。
- 外国籍の方は「国籍」の欄の記入も忘れずに。
- 過去に氏名や住所、役職等に変更がある場合は、「変更日」や「旧氏名」などの記載も必要です。
✍ ポイント:書類作成前に、戸籍謄本・住民票・登記簿謄本を手元に用意し、内容に齟齬がないよう確認しましょう。
提出前のチェックリスト:書類不備を防ぐために
申請書類は完璧に揃っていてこそ意味があります。提出前には以下の点を確認しておきましょう。
必要添付書類の例
- 本書類(役員等の略歴書)
- 住民票(個人ごとに)
- 身分証明書(破産や成年被後見の有無を確認)
- 登記されていないことの証明書(成年後見制度に関する証明)
※提出不要とされている自治体もあるため、事前確認が必要です。
📌 まとめ:自治体により必要書類や書式が異なるため、必ず最新の「手引き」や公式様式を確認しましょう。
申請手続き:実務担当者のためのポイント
- 最新の様式は必ず提出先都道府県の公式サイトで取得(印刷前にバージョン確認)
- 書類は黒インク・ボールペンで丁寧に手書き、または入力可のPDF活用
- 申請窓口への持参前に、チェックリストでの最終確認が鉄則
困ったときは:専門家への相談で安心を得よう
行政書士のサポート活用
建設業許可申請の専門家である行政書士に相談すれば、次のようなメリットがあります:
- 書類の作成・チェック・提出代行までワンストップで対応
- 自社の状況に応じた最適な手続きを提案してくれる
- 不備による再提出のリスクを大幅に軽減
初回無料相談の活用も有効
多くの行政書士事務所が、初回無料相談を実施しています。まずは気軽に問い合わせ、自社に必要な手続きと負担を把握するところから始めましょう。
まとめ:正確な書類作成が「許可取得」の第一歩
建設業許可の取得には、多くの書類と丁寧な準備が求められます。その中でも、本書類は審査の出発点となる重要な資料です。
内容に不備があれば、申請の遅延や不受理、最悪の場合は却下の原因にもなります。
このガイドで紹介したポイントをしっかり押さえ、正確かつ丁寧に書類を作成しましょう。
不安がある場合は、行政書士などの専門家の力を借りて、スムーズな申請を目指すことをおすすめします。