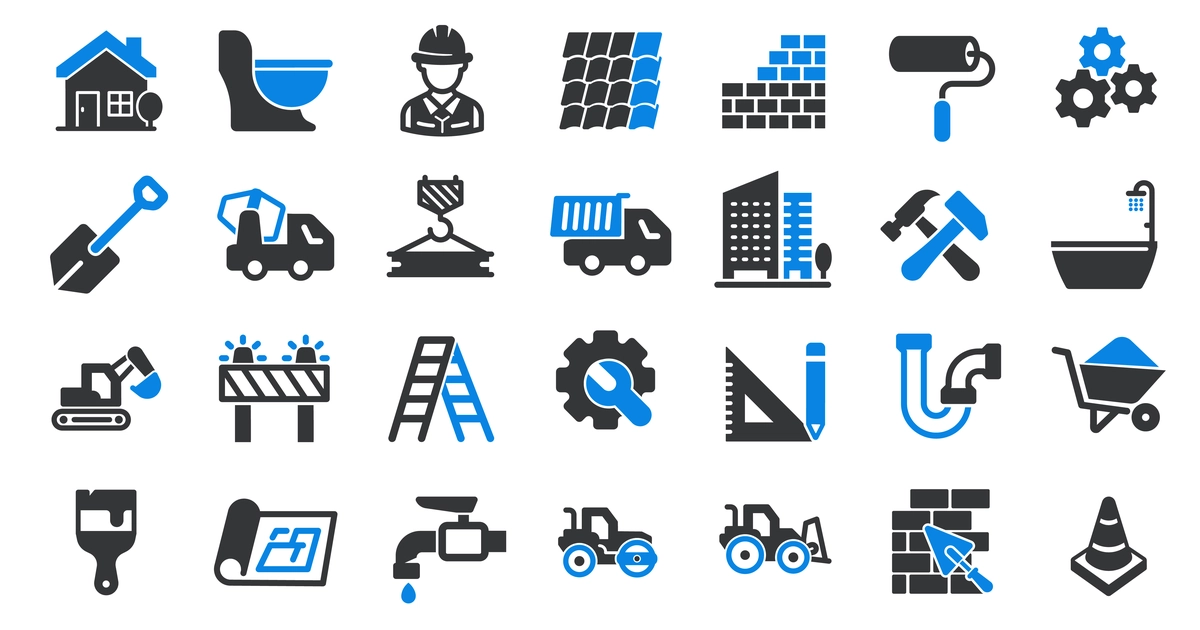建設業の許可を取得するには、自社の業務がどの業種に該当するのかを正しく判断することが不可欠です。この記事では、国土交通省が定める29業種それぞれの内容を、実務的な視点から詳しく解説します。さらに、業種ごとの工事例や判断のヒント、よくある混同パターンも紹介し、初めて建設業許可を取得する方にも分かりやすい構成となっています。
建設業許可の種類とは?29業種を体系的に理解しよう
建設業許可29業種 一覧と分類
建設業許可は、請け負う工事の種類によって、一式工事業(2業種)と専門工事業(27業種)の計29業種に分類されています。それぞれの工事に特有の技術・経験が求められるため、許可を取得する際には、実際に請け負う工事内容に応じた業種を選ぶ必要があります。
- 一式工事業(2業種)
- 建築一式工事業
- 土木一式工事業
- 専門工事業(27業種)
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
- 左官工事業
- 建築工事業
一式工事と専門工事の違い
一式工事とは、複数の専門工事を総合的に管理・統括して行う大規模な工事を指します。たとえば、ビルを建設する「建築一式工事」や、道路や橋を造る「土木一式工事」がこれに該当します。
一方で、専門工事とは、特定の分野に特化した工事を行うもので、電気工事や管工事、内装仕上工事などが代表例です。自社が主に行う業務がどちらに該当するかを確認し、適切な業種の許可を取得することが重要です。
許可取得前に確認すべきポイント
自社が行う工事内容を明確にする
まずは自社が請け負う予定の工事内容を洗い出しましょう。建物の新築か、道路の舗装か、それとも電気設備の施工か。これにより取得すべき業種の選定がスムーズになります。
工事の一部を下請に出す場合でも、元請として関与する工事全体を見渡して判断しましょう。
附帯工事の取り扱いに注意
許可を取得した業種に「附帯」する工事は、原則として別途許可を要しません。たとえば、建築一式工事の一環で行う小規模な電気工事などが該当します。
ただし、その附帯工事が主たる工事よりも重要と判断される場合は、別業種の許可が必要です。判断に迷う場合は、事前に行政庁や専門家に相談しましょう。
許可不要な「軽微な工事」とは?
以下の条件を満たす場合、建設業許可は不要です(ただし、社会的信用・入札要件などを考慮し取得する企業も多いです):
- 建築一式工事:①請負金額が1,500万円未満 または ②延べ床面積150㎡未満の木造住宅
- その他の工事:請負金額が500万円未満
※「いずれかの条件を満たせば軽微」とされます。材料費や労務費を含めた総請負金額で判断されるため、見積もりの内訳にも注意が必要です。
これらは建設業許可が不要ですが、「反復継続性」があれば許可取得を推奨します。
各業種の詳細と判断のヒント(代表的な8業種例)
とび・土工・コンクリート工事業
- 工事内容例:足場組立、鉄骨組立、地盤改良、山留工事、掘削、杭打ちなど。
- 判断ポイント:現場作業中心で重量物の据付を伴う作業が主なら該当。
- よくある誤解:「とび・土工」と「鋼構造物工事」との違いに注意(加工の有無が基準)

内装仕上工事業
- 工事内容例:クロス貼り、床仕上げ(フローリング、カーペット)、間仕切りなど。
- 判断ポイント:建物完成後の美装・機能的な内装が中心なら該当。
- 誤認例:「軽天工事」は鋼構造物ではなく、基本的に内装仕上工事に分類。

塗装工事業
- 工事内容例:建築物や鉄骨の塗装、防錆、防食処理など。
- 判断ポイント:塗膜を形成する作業かどうかが判断の分かれ目。
- 誤認例:防水目的の塗布は「防水工事」になる場合も。

電気工事業
- 工事内容例:屋内外配線、照明、受変電設備、太陽光発電など。
- 判断ポイント:電気設備の設置・改修が中心かどうか。
- 注意点:別途「電気工事士法」の資格要件にも注意。

解体工事業
- 工事内容例:木造・RC・鉄骨建築の解体、アスベスト除去など。
- 判断ポイント:建物を壊す行為が中心。
- 補足:2016年より新設された業種。

管工事業
- 工事内容例:給排水衛生設備、空調設備、冷暖房配管、ガス管敷設、浄化槽設置など。
- 判断ポイント:水・空気・ガス等の流体を配管によって搬送・処理する設備工事。
- 誤認例:冷媒配管は管工事、電気配線は電気工事と混同しやすい。

大工工事業
- 工事内容例:木造軸組の組立、床・壁・屋根の木工事、造作材の取付けなど。
- 判断ポイント:木材を主とした建築物の構造体や内装の造作が中心。
- 注意点:軽微な木工事ではなく、建物の構造に関わる工事が該当。

機械器具設置工事業
- 工事内容例:エレベーター、クレーン、プラント、ボイラーなどの設置工事。
- 判断ポイント:機械本体の設置・据付・固定・試運転などを含む工事。
- 誤認例:電気接続は電気工事、配管は管工事と区別が必要。

これらの業種解説を通じて、自社の業務内容がどの許可に該当するか、より明確にイメージできたのではないでしょうか。実際の申請前には専門家のアドバイスも活用しながら、適切な業種選定を行いましょう。
よくある混同例と対比表
| 業種A | 業種B | 判断基準 |
|---|---|---|
| 左官工事 | タイル・レンガ工事 | 塗る:左官/貼る:タイル |
| 鋼構造物工事 | とび・土工工事 | 工場で加工:鋼構造物/現場で組立:とび |
| 防水工事 | 塗装工事 | 主目的が防水:防水/仕上げ:塗装 |
| 建築一式 | 専門工事 | 複数専門を総合的に管理:一式 |
自社に必要な業種が分かる!チェックリスト
以下のチェックリストを参考に、自社の工事内容に該当する業種を見つけましょう。複数に当てはまる場合は、主要な業務内容を基準に判断し、必要に応じて複数業種を取得するのが安心です。
- □ 自社は鉄骨を加工して設置している → 【鋼構造物工事】
- □ クロス貼り、床貼りなど仕上げ工事が中心 → 【内装仕上工事】
- □ 太陽光発電の設置工事を受注している → 【電気工事業】
- □ アスベストを除去してから建物を解体している → 【解体工事業】
- □ 木造住宅の骨組みから造作工事までを担っている → 【大工工事業】
- □ 給排水・空調・冷暖房・ガス管等の配管工事を行っている → 【管工事業】
- □ エレベーターや大型プラント設備を据え付ける → 【機械器具設置工事業】
- □ 外壁や屋根などへの塗装工事を請け負っている → 【塗装工事業】
- □ 雨漏り防止などの防水処理が中心 → 【防水工事業】
- □ 敷地内に植栽・庭園・外構を整備している → 【造園工事業】
- □ 建物の屋根の葺き替え・板金工事を行っている → 【屋根工事業】
- □ インターホンや監視カメラ、通信機器の設置を行っている → 【電気通信工事業】
- □ ガラスやサッシの取り付け、交換を行っている → 【ガラス工事業】
- □ 水道本管から建物への引込管工事を行っている → 【水道施設工事業】
- □ 消防設備(スプリンクラー、火災報知器など)を設置している → 【消防施設工事業】
よくある質問(FAQ)
建設業許可の取得や業種の選定に関して、多くの事業者が抱える疑問点をまとめました。初めての申請で不安な方や、要件に関する判断に迷っている方は、ぜひこのセクションを参考にしてください。
Q:複数の業種に該当する場合は?
A:主要な工事内容に合わせて申請業種を選びます。必要に応じて複数業種を取得可能です。
Q:建築一式の許可があれば他の専門工事もできる?
A:いいえ、原則として各専門工事について個別の許可が必要です(軽微工事を除く)。
Q:許可を取らないで工事をしたら?
A:無許可営業は建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象です。
Q:許可取得までにどれくらいの期間がかかる?
A:自治体にもよりますが、書類が整っていれば申請から約30~45日で許可が下りるケースが多いです。
Q:個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
A:可能です。ただし、法人と同様に要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的要件など)を満たす必要があります。
Q:将来的に新しい工種に参入したい場合は?
A:必要な業種を追加で申請(業種追加申請)することで対応可能です。工事開始前に追加しておきましょう。
Q:どの業種に該当するか自分で判断できない場合は?
A:判断が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することで確実な申請が可能です。
建設業許可の取得要件
経営業務の管理責任者
建設業の経営に関する経験がある常勤役員等を1名置く必要があります。2020年10月の法改正により、「業種ごとの経験」は不要となりました。
例:法人の代表取締役として建設業を5年以上経営していた経験などが該当します。
専任技術者の配置
各営業所に、建設工事に関する知識・経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。要件は以下のいずれかです:
- 国家資格(例:1級建築士、施工管理技士)
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験
- 実務経験10年以上(学歴不問)
業種ごとに認められる資格が異なるため、事前確認が必要です。
財産的基礎
新規申請の場合、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(融資証明など)
※更新申請では要件が緩和されますが、特定建設業許可の場合はより厳しい財務要件が課されます。
許可取得にかかる費用
申請手数料
申請種別によって手数料は異なります。
- 新規知事許可:90,000円(収入証紙等で納付)
- 新規大臣許可:150,000円
- 更新:50,000円~
- 業種追加:50,000円~(知事)
※不許可でも返還されません。各都道府県または国土交通省のHPで最新情報を確認しましょう。
行政書士への依頼費用
- 新規申請:10~20万円前後
- 更新申請:5~10万円前後
- 業種追加:個別見積もり
行政書士によって対応の質や料金体系は異なります。建設業許可に強い事務所を選ぶことがスムーズな取得への近道です。
その他実費
- 登記簿謄本:約600円
- 印鑑証明書:約300円
- 納税証明書:約400円
- 住民票など:各市区町村により異なる
必要書類の有効期限にも注意し、早めの準備が重要です。
許可取得後の注意点
許可の更新は5年ごと
許可は5年ごとに更新が必要です。有効期限の3ヶ月前から手続きが可能で、期限を過ぎると失効扱いとなります。
変更届の提出義務
以下の変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません:
- 商号・所在地の変更
- 役員・令3条使用人の変更
- 資本金の増減
遅延や未提出は建設業法違反となり、更新・変更申請が通らなくなる可能性もあります。
年1回の決算変更届
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、次の書類を提出する必要があります:
- 貸借対照表・損益計算書
- 完成工事高内訳書
- 工事経歴書 など
正確な会計処理が前提となるため、税理士・行政書士のサポートを受けることが推奨されます。
まとめ|建設業許可の正しい理解が未来を拓く
建設業許可は、単なる資格ではなく、法令遵守・社会的信用・入札資格を確保するための重要な制度です。29業種のうち、どれを取得すべきかを見極めるには、工事内容の正確な把握と法制度への理解が不可欠です。
不明点や不安がある場合は、建設業許可に強い行政書士に相談し、確実な取得・維持を図りましょう。