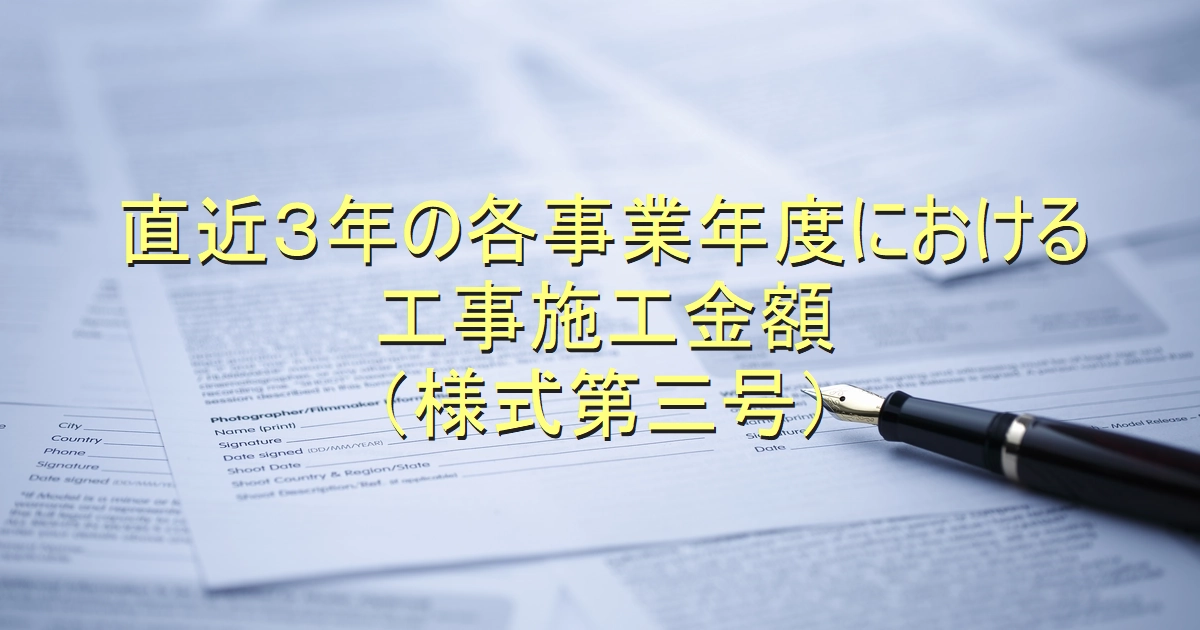建設業許可の申請書類には、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を記載した「様式第三号」の提出が求められるケースがあります。本記事では、記入の際に押さえておくべきポイントや記載方法を、元請・下請の区分や税抜・税込の取扱いなども含めて分かりやすく解説します。
「直前3年の工事施工金額」とは?実績確認のための重要資料
「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、建設業許可の新規申請・業種追加・更新などにおいて、過去の工事実績を確認するための書類です。
この様式を通じて、申請者が継続的に建設業を営んでいるか、また工事の実績があるかを行政庁が確認します。経営事項審査(経審)のように点数評価が行われるわけではありませんが、適正な許可判断の根拠資料として扱われます。
記載ミスや金額の誤記があると、補正対応や審査の遅延につながる可能性もあるため、慎重な記載が求められます。
様式第三号とは?共通のフォーマットで提出
「様式第三号」は国土交通省の定める統一書式で、全国どの自治体でも使用されます。申請者の規模や業種に関係なく、形式は共通です。年度ごとに、請け負った建設工事を工種別に分類し、元請・下請に区分して施工金額を記載します。
この様式は、企業の業務実績を明確に示すための資料であり、特に一般建設業許可の実績確認の場面で重要な役割を果たします。
提出が必要となる代表的なケース
以下のような申請では、様式第三号の提出が求められます:
- 建設業許可の新規申請(特に一般建設業)
- 業種追加申請(要件確認が必要な場合)
- 許可更新(一部ケースで求められる)
一方で、知事許可から大臣許可への変更や、単なる役員変更などでは、この様式が不要な場合もあります。事前に申請先行政庁の手引きや案内を確認することが重要です。
書き方のポイント(元請・下請の区分)
元請工事の記載例
元請として受注した工事は、各事業年度ごとに工事の種類別に分類し、それぞれの税抜施工金額を記載します。複数の工事がある場合は、正確に合算し、内訳を帳簿等で確認できるように準備しておきましょう。
使用する金額は、原則として 契約金額ベース(完工ベース)で記載します。
下請工事の記載例
下請として施工した工事についても、元請からの契約に基づいた金額を記載します。請求書や工事台帳を基に、工種別に整理し、年度別に分類して金額を記載します。
【注意】
一部のブログ等で「CCUS(建設キャリアアップシステム)に施工金額が記録されている」との記述がありますが、CCUSには施工金額の記録機能はありません。 金額の確認には契約書や請求書などの書面を用いてください。
税込・税抜の取扱いに注意
施工金額の記載は、原則として税抜金額で行います。ただし、自治体によって異なる運用がされている場合があるため、必ず事前に申請先行政庁の指示に従うようにしましょう。
金額の単位についても、「千円単位」などの指定があるため、手引きや記載例をよく確認してください。
書類作成時のチェックポイント
1. 金額の整合性確認
施工金額は、決算書や工事台帳、請求書控えなどをもとに確認し、整合性が取れていることが重要です。誤りがある場合、修正理由を求められる可能性があります。
2. 記載漏れの防止
特に少額工事や年度をまたいだ工事は、記載漏れになりやすいため注意が必要です。全工事の台帳・契約書をもとに一覧化し、もれなく集計しましょう。
専門家に相談するメリット
建設業許可の申請には専門的な知識が必要です。行政書士などの専門家に相談することで、記載ミスの防止や審査のスムーズ化が図れます。
特に様式第三号は、見落としやすい工種分類や金額の整理が必要になるため、プロのサポートを受けることで安心して申請が行えます。
電子申請も可能に
建設業許可の申請は、一部自治体で電子申請に対応しています。電子証明書やGビズIDを取得すれば、専用のWebフォームを通じて申請が可能です。
ただし、システムの利用には事前準備が必要なため、自治体の案内ページを事前に確認しましょう。
まとめ:正確な記載で許可取得をスムーズに
「直前3年の工事施工金額」は、建設業許可申請における実績確認の要となる書類です。税抜金額の統一や工種別の分類、記載漏れの防止といった基本を押さえた上で、正確に記載することが求められます。
不安な場合は専門家に相談し、スムーズな許可取得を目指しましょう。