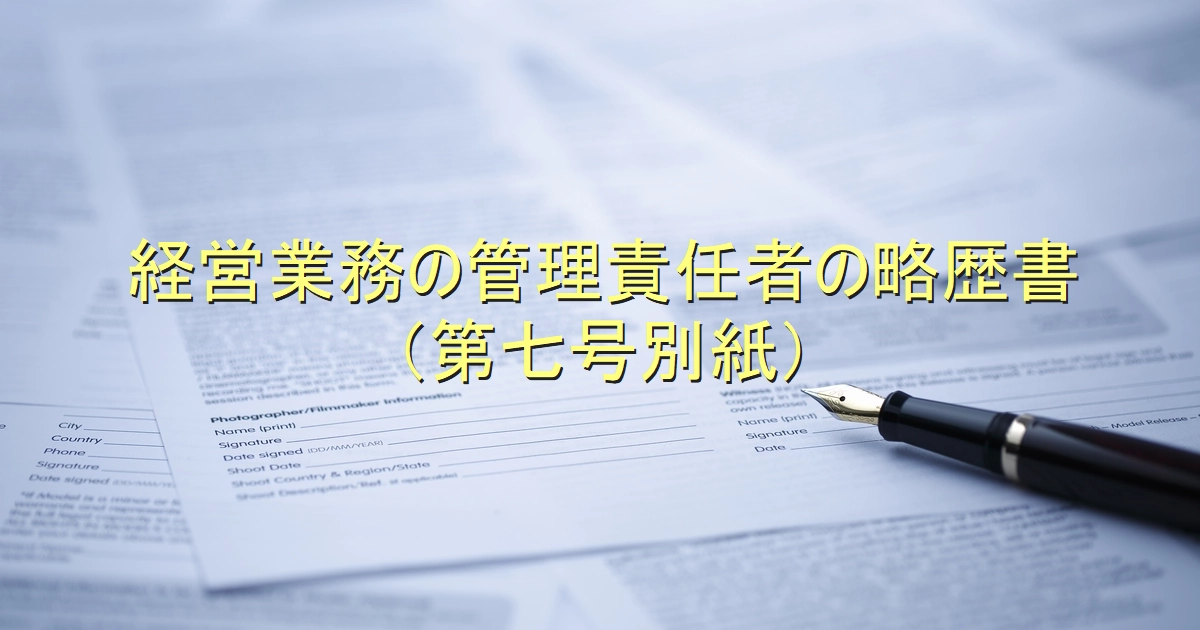建設業許可の申請において、「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」としての要件を満たしていることを証明するためには、略歴書の提出が求められる場合があります。本記事では、略歴書の役割、記載項目、作成時の注意点、そして専門家に依頼するメリットまで、制度に基づいて分かりやすく解説します。
略歴書の役割と提出が必要な場面
経営業務の管理責任者とは?
建設業法上、一定の経験や知識を有する者が「経営業務の管理責任者」として、許可業者の経営を実質的に管理することが求められています。略歴書は、その人物が法定要件を満たしていることを証明する書類です。
提出が必要となるケース
略歴書は、以下のような場合に必要となります:
- 建設業許可の新規申請で、要件を満たす人物を立てる場合
- 経営業務の管理責任者が変更となる場合(役員の交代等)
- 業種追加や合併により、新たに経営業務の管理責任者を立てる必要がある場合
更新申請時は、基本的に経営業務の管理責任者が変わらなければ略歴書は不要です。
略歴書の記載内容とポイント
記載すべき主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 略歴書の提出者本人 |
| 生年月日 | 年齢確認と本人特定に必要 |
| 住所 | 通常、住民票と一致させる |
| 最終学歴 | 学校名、学部、卒業年月(補足情報として) |
| 職歴 | 建設業に関する経営経験が中心(役職、業務内容含む) |
| 賞罰 | あれば詳細に、なければ「なし」と明記 |
職歴の記載ポイント
建設業許可の要件を満たすには、一定期間(原則5年)にわたる経営管理経験が求められます。そのため、記載する職歴は以下の観点で具体的に書きましょう:
- 会社名(法人名と所在地)
- 在籍期間(西暦で明記)
- 役職名(取締役、専務など)
- 担当業務の内容(経理、人事、契約管理等)
- 関与した建設業種やプロジェクト名(あれば)
記載内容が抽象的すぎると、審査に通らない可能性があります。
賞罰欄の注意点
賞罰がある場合は正確に記載しなければなりません。虚偽や未記載は、建設業法第29条(不正手段による許可取得)に該当する可能性があります。不明点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
よくある誤解と注意点
❌「更新申請でも略歴書が必ず必要」
→ 経営業務の管理責任者に変更がなければ、通常略歴書の提出は不要です。
❌「メールアドレスや電話番号を略歴書に記載」
→ 国交省の標準様式に、これらの項目は含まれていません(ただし申請書全体で別途連絡先の記載を求められる場合あり)。
❌「卒業証明書や資格証明書が添付書類として必要」
→ 略歴書の補強資料としては主に、「登記事項証明書」「在籍証明書」「請負契約書の写し」などが用いられます。卒業証明書などは、技術者要件等で求められることが多く、目的を混同しないよう注意が必要です。
添付書類と提出先の確認
略歴書に記載する経歴を証明するため、以下のような証拠書類の提出を求められる場合があります:
- 在籍証明書や辞令
- 商業登記簿謄本(役員歴の確認)
- 請負契約書・見積書・請求書(事業実績の裏付け)
都道府県によって取扱いが異なるため、事前に申請先の建設業課に確認することが重要です。
専門家に依頼するメリット
略歴書は単なる履歴書ではなく、建設業法の厳格な要件に基づいて作成される審査資料です。不備があると、許可の不交付や審査の長期化につながります。
専門家(行政書士)に依頼することで得られるメリット
- 制度・法令に基づいた正確な記載をサポート
- 添付書類の確認・手配
- 申請書全体の整合性チェック
- 曖昧な記憶に基づかない証拠主義の徹底
特に初めての申請や、役員構成が複雑な場合は、専門家の関与が許可取得の大きな安心材料になります。
まとめ:略歴書作成は「審査の第一関門」
経営業務の管理責任者の略歴書は、建設業許可申請における「信用・実績の証明書」です。制度に則った記載と裏付け資料の整備によって、スムーズかつ確実な許可取得につなげましょう。
作成に不安がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士への相談を検討するのが確実です。誤記や虚偽記載のない、信頼される略歴書づくりを目指しましょう。