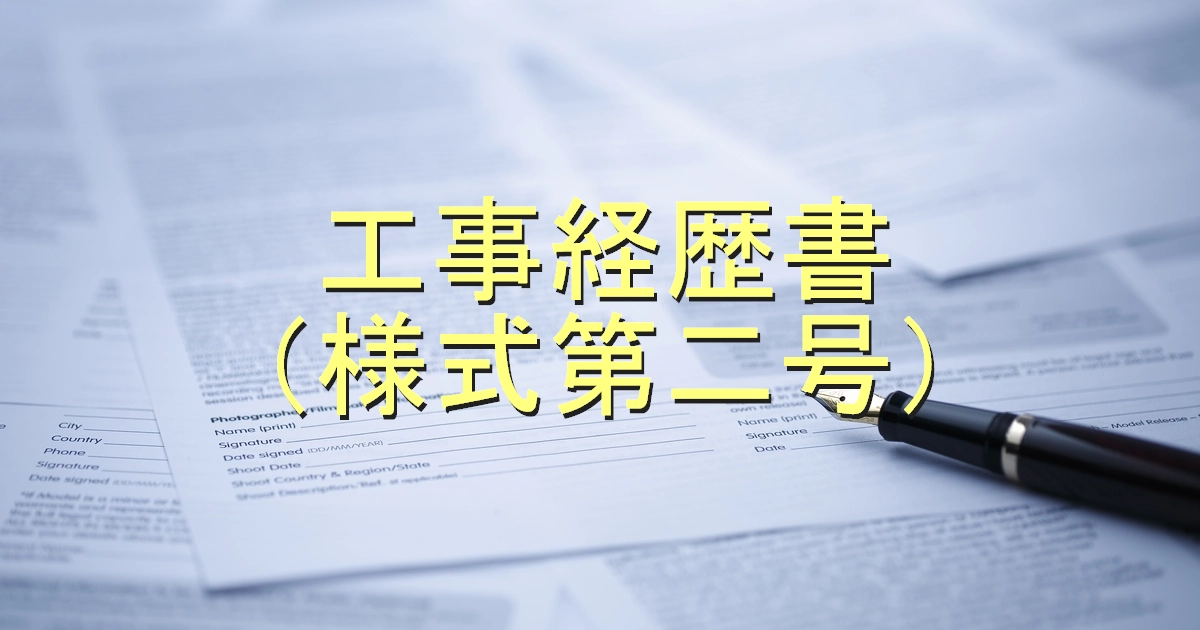建設業許可の申請に不可欠な工事経歴書。本記事では、その書き方を徹底解説します。記入例から注意点、よくある疑問まで、建設業許可申請をスムーズに進めるための情報が満載です。初めて工事経歴書を作成する方も、再確認したい方も必見です。
工事経歴書とは?建設業許可における重要性と役割
工事経歴書の基本:何が記載されているのか
工事経歴書は、建設業許可を申請する際に、 自社の技術力や経営状況を証明するために不可欠な書類です。 具体的には、過去に手掛けた工事の名称、 工事場所、工事期間、そして工事金額などが詳細に記載されます。 これらの情報は、建設業許可を管轄する行政機関が、 申請者の適格性を判断するための重要な材料となります。
特に、新規に建設業許可を申請する企業や、 過去の実績が少ない企業にとっては、 工事経歴書の内容が審査結果に大きく影響するため、 正確かつ詳細な情報提供が求められます。 工事経歴書は、単なる過去の記録ではなく、 将来の事業展開を左右する可能性もある重要な書類であることを理解し、 慎重に作成する必要があります。記載漏れや誤りがないよう、 十分な注意を払いましょう。
工事経歴書が必要な理由:許可の種類と影響
建設業許可は、請け負うことができる工事の種類や金額によって、 いくつかの種類に分類されます。 これらの許可の種類に応じて、工事経歴書に求められる情報や、 その重要性が大きく異なります。 例えば、特定建設業許可を申請する場合、 一定規模以上の工事を請け負うための高度な技術力や、 経営能力が求められるため、工事経歴書には、 これらの能力を証明するための詳細な情報が必要となります。
また、過去に手掛けた工事の規模や種類が、 申請する許可の種類に適合しているかどうかも審査されるため、 工事経歴書の内容は、許可取得の可否に直接影響します。 したがって、申請する許可の種類を正確に理解し、 それに応じて適切な工事経歴書を作成することが重要です。 不備があると、許可申請がスムーズに進まない可能性があります。
工事経歴書がないとどうなる?
工事経歴書は、建設業許可申請において、 必須の添付書類の一つとされています。 もし工事経歴書を提出できない場合、 原則として建設業許可の申請は受理されません。 これは、建設業法に基づいて定められた手続きであり、 例外は認められていません。 特に、新規に建設業許可を申請する企業にとっては、 過去の工事実績を証明する唯一の手段が工事経歴書であるため、 その重要性は非常に高いと言えます。
過去に建設業許可を持っていた企業であっても、 更新申請の際には、直近の工事実績を証明するために、 工事経歴書が必要となります。 したがって、建設業を営む上で、工事経歴書は常に適切に管理し、 必要な時にすぐに提出できるように準備しておくことが重要です。
工事経歴書の書き方:記入例と注意点
工事概要の書き方:工事名、場所、期間
工事経歴書における工事概要の記載は、 許可取得の審査において非常に重要な要素となります。 工事名は、具体的にどのような工事であったかを明確に示す必要があります。 例えば、「〇〇邸新築工事」や「△△ビル改修工事」のように、 工事の内容が具体的にわかるように記載しましょう。 工事場所は、都道府県名だけでなく、市区町村名、 地番まで正確に記載することが求められます。 工事期間は、着工日と竣工日を正確に記載します。 これらの日付は、契約書や工事完了報告書などの 客観的な資料に基づいて記載する必要があります。
これらの情報を正確に記載することで、審査官は、 申請者が過去にどのような工事を手掛けてきたのか、 その規模や内容を正確に把握することができます。 不明な点があれば、関係書類を再度確認し、 正確な情報を記載するように心がけましょう。
工事金額の書き方:消費税の扱いと注意点
工事経歴書に記載する工事金額は、消費税を含まない金額を記載することが原則です。 これは、建設業許可の審査において、 企業の技術力や経営規模を評価する際の基準となるためです。 消費税を含んだ金額を記載してしまうと、 企業の規模が実際よりも大きく見えてしまい、 正確な評価が難しくなる可能性があります。
工事金額の単位にも注意が必要です。 一般的には、千円単位で記載し、百円以下は切り捨てます。 この点も、記載ミスが多い箇所ですので、十分に注意しましょう。 過去に建設業許可の申請を行ったことがある場合は、 過去の申請書類を確認し、同じ形式で記載するように心がけましょう。 特に、過去に審査で指摘された箇所については、 再度確認し、誤りのないように記載することが重要です。
配置技術者の書き方:資格と経験
工事経歴書には、その工事に配置された技術者の情報も記載する必要があります。 配置技術者とは、工事現場における技術的な管理や監督を行う者のことで、 建設業法によって、一定の資格を持つ者が配置されることが義務付けられています。 工事経歴書には、配置技術者の氏名、 保有する資格、そしてその資格を取得した年月日などを正確に記載します。
また、その技術者が実際に工事に従事した期間や、 担当した業務内容なども記載することが望ましいです。 配置技術者の資格によっては、資格証の写しなどの添付書類が必要になる場合もあります。 配置技術者の選任は、建設業法に基づいて適切に行う必要があり、 その記録を工事経歴書に正確に反映させることが重要です。 不明な点があれば、専門家や行政機関に相談することをおすすめします。
【重要】工事経歴書を作成する際の注意点
金額の大きい工事から記載する
工事経歴書を作成する際には、記載する工事の順番にも注意が必要です。 一般的には、工事金額の大きいものから順番に記載するのが望ましいとされています。 これは、審査を行う行政機関が、申請者の企業の規模や、 実績を把握しやすくするためです。大規模な工事を数多く手掛けている企業は、 それだけ技術力や経営力があると判断される可能性が高くなります。
ただし、必ずしもすべての工事を金額順に記載しなければならないわけではありません。 例えば、特定の種類の工事(例:公共工事、専門工事など)を、 優先的に記載したい場合は、その旨を明記した上で、 順番を入れ替えることも可能です。 重要なのは、審査官が企業の強みや特徴を理解しやすいように、 工夫して記載することです。記載順序についても、慎重に検討しましょう。
対象期間は申請する期の直前期
工事経歴書に記載する工事の対象期間は、原則として、 建設業許可の申請を行う事業年度の直前の事業年度となります。 例えば、3月決算の企業が5月に建設業許可の申請を行う場合、 工事経歴書には、前年の4月1日から今年の3月31日までの期間に 完了した工事を記載する必要があります。 この期間を間違えてしまうと、審査がスムーズに進まない可能性があります。
ただし、事業年度の途中で許可の更新申請を行う場合など、 例外的に対象期間が異なるケースもあります。 また、過去に遡って工事経歴を修正する必要がある場合も、 対象期間の考え方が変わってくることがあります。 不明な点がある場合は、必ず行政機関や専門家に確認するようにしましょう。 正確な期間を把握し、間違いのない工事経歴書を作成することが重要です。
虚偽記載は絶対にしない
工事経歴書に虚偽の内容を記載することは、絶対に避けなければなりません。 虚偽記載は、建設業法に違反する行為であり、 重大な法的責任を問われる可能性があります。 例えば、実際には行っていない工事を記載したり、 工事金額を水増ししたり、配置技術者の資格を偽ったりする行為は、 すべて虚偽記載に該当します。 虚偽記載が発覚した場合、建設業許可が取り消されるだけでなく、 営業停止命令や罰金などの厳しい処分が科せられることがあります。
また、刑事責任を問われる可能性もあります。 工事経歴書は、正確な情報を基に、正直に作成することが重要です。 もし記載内容に不安がある場合は、専門家や行政機関に相談し、 適切なアドバイスを受けるようにしましょう。虚偽記載は、 企業にとって取り返しのつかない事態を招く可能性があることを、 常に念頭に置いておきましょう。
ケース別:工事経歴書の記入例
新設法人の場合:実績がない時の書き方
新設法人の場合、過去の工事実績がないため、 工事経歴書に記載する内容がないというケースが考えられます。 しかし、このような場合でも、工事経歴書を提出する必要があります。 実績がない場合は、その旨を正直に記載し、 今後の事業計画や、技術者の経歴などを詳細に記述することで、 審査官に企業の将来性や技術力をアピールすることが重要です。
例えば、 「現在、〇〇工事の受注に向けて準備中であり、 〇〇株式会社との間で業務提携を締結している」といった具体的な情報を記載することで、 審査官に安心感を与えることができます。 また、代表者や技術者の過去の職務経歴や、 保有する資格などを詳細に記載することも有効です。 実績がないからといって諦めずに、 できる限りの情報を盛り込むように心がけましょう。 熱意と誠意をもって対応することが、許可取得への近道となります。
共同企業体(JV)の場合:出資割合と工事分担
複数の建設業者が共同で工事を行う場合、 共同企業体(JV)を設立することがあります。 JVとして工事を行った場合、工事経歴書には、 JV全体の工事実績だけでなく、各構成員の出資割合や工事分担の内容も 明確に記載する必要があります。
例えば、A社が60%、B社が40%を出資してJVを設立し、 〇〇工事を行った場合、工事経歴書には、 A社の実績として工事金額の60%を、B社の実績として40%を記載します。 また、A社が主に土木工事を担当し、B社が主に電気工事を担当した場合、 その旨も明記する必要があります。
JV協定書の写しや、 工事分担に関する契約書などの添付書類が必要になる場合もあります。 JVにおける工事実績は、各構成員の技術力や経営能力を評価する上で、 重要な要素となるため、正確かつ詳細に記載することが重要です。 記載漏れや誤りがないよう、関係書類を十分に確認しましょう。
経審を受けない場合の書き方
経営事項審査(経審)とは、公共工事に入札する際に必要となる審査のことです。 経審を受ける場合は、工事経歴書の内容が、 経営状況や技術力を評価するための重要な資料となります。 しかし、経審を受けない場合でも、建設業許可の申請には、 工事経歴書が必要となります。 経審を受けない場合の工事経歴書の書き方は、 基本的に経審を受ける場合と変わりません。
ただし、経審を受ける場合に比べて、 審査のポイントが異なる場合があります。 例えば、経審では、企業の財務状況や、 技術者の数などが重視されますが、 経審を受けない場合は、過去の工事実績や、 安全管理体制などがより重視される傾向があります。 したがって、経審を受けない場合は、 工事経歴書に、過去の工事実績や安全管理体制について、 より詳細に記載することが重要です。
まとめ:工事経歴書作成のポイントと建設業許可申請の成功
工事経歴書の作成は、建設業許可申請の成否を大きく左右する重要なプロセスです。 本記事では、工事経歴書の基本的な書き方から、 注意点、ケース別の記入例などを詳しく解説しました。 これらの情報を参考に、正確かつ丁寧に工事経歴書を作成し、 スムーズな建設業許可取得を目指しましょう。
工事経歴書は、単なる過去の記録ではなく、 企業の技術力や経営能力を証明するための重要なツールです。 記載内容に誤りや不備があると、許可申請が却下されたり、 審査に時間がかかったりする可能性があります。 不明な点があれば、専門家や行政機関に相談し、 適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
建設業許可を取得することは、企業の信頼性を高め、 事業拡大のチャンスを広げることにつながります。 工事経歴書の作成を通じて、自社の強みや実績を再確認し、 自信を持って建設業許可申請に臨みましょう。